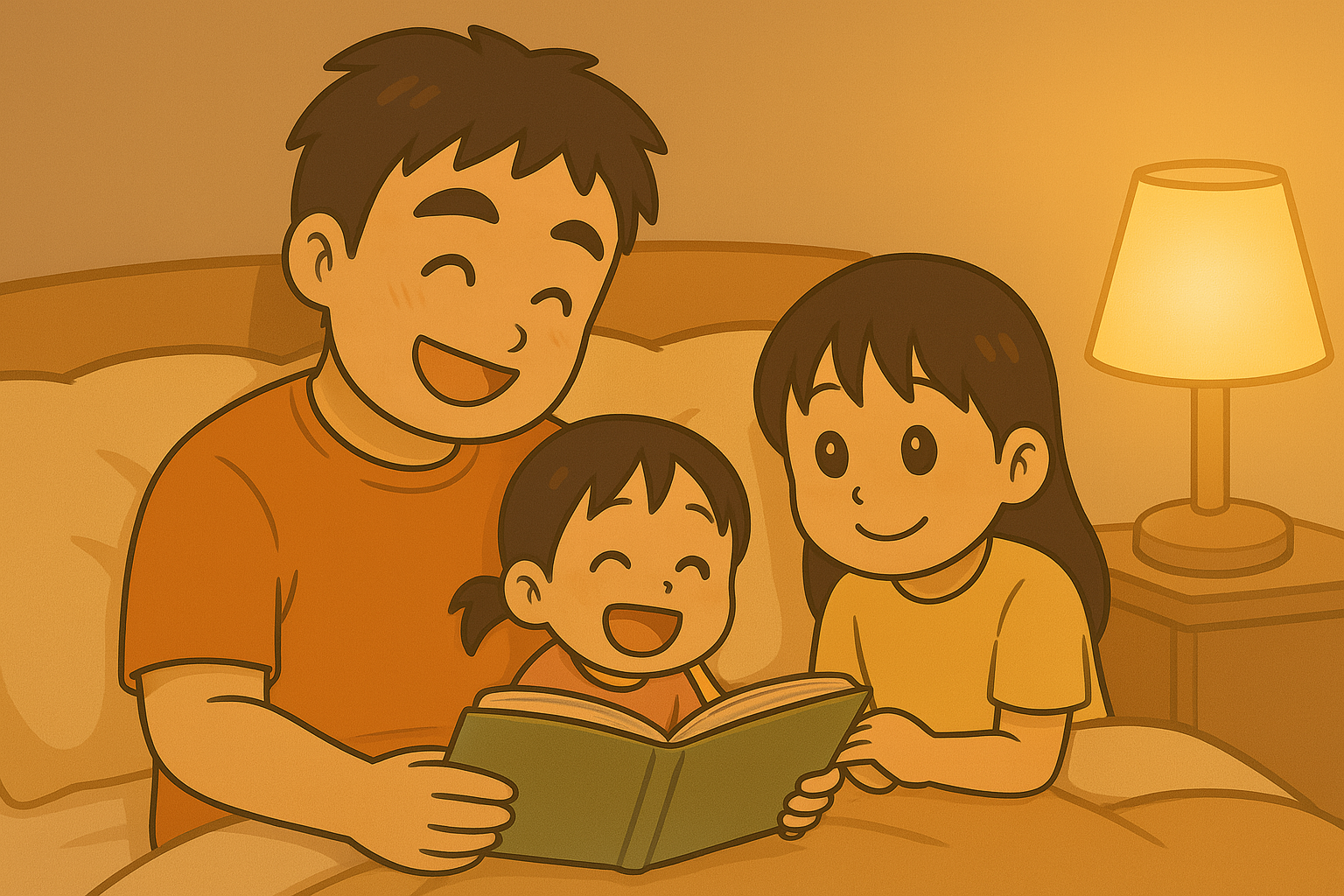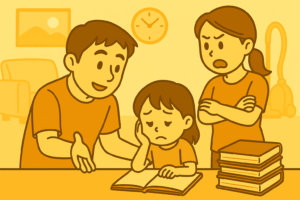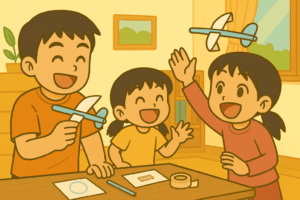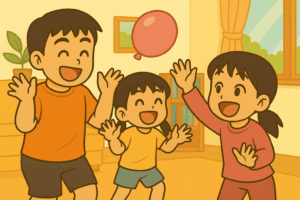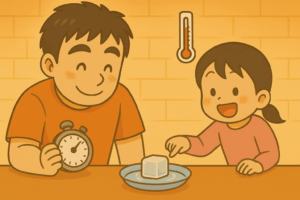こんにちは、二児の娘を育てるパパブロガーのひろゆきです。わが家では毎晩の読み聞かせが“1日のしめくくり”。同じ本でも、読む声色や間の取り方で子どもの反応が変わるのがおもしろくて、ついつい演じたくなります。この記事では、実際に親子で何十回と読んで「パパが読みやすい/子どもが食いつく」と感じた絵本を10冊、年齢目安や読み方のコツとともに紹介します。最後に、時間がない日の時短テクや本選びのポイントもまとめました。
[toc]
このリストの前提:パパ視点の選書基準
- 声に出すと気持ちいいリズム(擬音・繰り返し・言い回しの面白さ)
- 演じ分けしやすい登場人物(低音・高音・ささやきなどで抑揚がつけやすい)
- 読み切り5分前後で寝かしつけ前にも使いやすい
- 0〜年長まで段階的に楽しめる(年齢が上がると別の見方で楽しめる)
- わが家の実読実績:子どもが「もう1回!」とリピート要求した回数が多い
おすすめ絵本10選(年齢目安つき)
1. めがねうさぎ(せなけいこ)|3歳〜
めがねを探すうさぎと、ちょっとおっちょこちょいなオバケの掛け合いが最高。
コツ:オバケのセリフは息を抜き気味の低音で、最後の「べろべろばあ」はテンポを一拍ためてから全開に。ビビりな子でも笑いに寄せやすい“怖かわいい”一冊。
2. 11ぴきのねこ ふくろのなか(馬場のぼる)|4歳〜
“ウヒアハ”など味のある言葉が耳に残り、パパも読んでいて楽しい。
コツ:11匹の合唱は少しだけ声を揃えて、オチはサラッと落とすと笑いが増幅。兄弟で掛け合いながら読むのも◎。
3. きょだいな きょだいな(長谷川摂子/降矢なな)|3歳〜
次々に巨大なものが現れるナンセンス絵本。ページをめくる“期待感”がすごい。
コツ:「きょだいな…」の言い出しを毎回少し溜め、ページ送りでドン!と見せる。テンポ芸が活きます。
4. わたしのワンピース(にしまきかやこ)|3歳〜
「ラララン ロロロン」のリズムと色柄の変化が美しい。
コツ:“ミシンの音”をささやきで入れると雰囲気が倍増。色や模様を一緒に言葉にして、親子の対話を増やしましょう。
5. とりかえっこ(さとうわきこ/二俣英五郎)|4歳〜
鳴き声を取り替えたらどうなる?という発想が大ヒット。
コツ:動物ごとに声色を変えると子どもの爆笑ポイントに。「む」の一言は“ドヤ顔+間”が決め手。
6. いろいろ ばあ(新井洋行)|0〜2歳
色と形、擬音のリズムが赤ちゃんの集中を引き寄せる。
コツ:顔の近くで「ばあ」を小刻みに。テンポ良く短く何度も読めるので、寝る前の最終1冊にも。
7. だるまさんが(かがくいひろし)|1〜3歳
“どてっ”などの擬態語が心地よく、身体あそびに発展しやすい。
コツ:ページと一緒に身体も動かす“見立て”読みでケラケラ笑いを量産。
8. てぶくろ(ウクライナ民話/エウゲーニー・M・ラチョフ)|4歳〜
動物が次々に入っていく“くり返し”の面白さは鉄板。
コツ:動物名のたびに声色とスピードを変え、最後の大混乱は早口で畳みかけると盛り上がる。
9. でんしゃにのって(とよたかずひこ)|3歳〜
駅ごとに出会いと別れがあり、穏やかな時間が流れる名作。
コツ:アナウンス風の抑揚や車輪のリズム「ガタンゴトン」を背景音のように。乗り物好きキッズに刺さります。
10. ぐりとぐら(なかがわりえこ/やまわきゆりこ)|3歳〜
言わずと知れた国民的名作。お料理の場面でお腹が鳴る親子続出。
コツ:料理工程を実況し、匂い・音・温度を想像させる言葉を足すと臨場感アップ。
読み聞かせのコツ:時間がなくても“質”は上げられる
- 最初の3行で世界に入れる声色:低めトーン+ゆっくり目で導入、3行後からテンポアップ。
- 「間」を恐れない:オチの前は1拍、見開きの大ゴマでは2拍。沈黙は演出です。
- セリフの主は指で指し示す:誰の台詞かが一目でわかるだけで集中が続く。
- “今日はここまで”のルールを先に宣言:「2冊読んだら電気を消す」のように事前合意を。
年齢別の選び方(わが家の実感)
0〜2歳:擬音・くり返し・大きな構図でOK。短い文×はっきりした色がベター。
3〜4歳:ストーリー性と「次どうなる?」の予測が楽しめる本が刺さる。
5〜6歳:心情描写・ユーモア・教訓がある本もスッと入る。読み終わりの対話が楽しい時期。
わが家の“リピート”ローテーション例(平日15分)
- 1冊目:短い擬音系でウォームアップ(2〜3分)
- 2冊目:物語系でしっかり堪能(5〜7分)
- おまけ:子どもが選んだ1冊を“超早口”or“ささやき”など遊び読み(2〜3分)
よくある質問(Q&A)
Q. 同じ本ばかり読みたがります。変えた方がいい?
A. 同じ本の繰り返しは理解と安心感を深めます。読む側が声の強弱や速さを変えて“同じ中の違い”を演出すると飽きません。
Q. 途中で飽きて立ち歩いてしまいます。
A. 身体が動くタイプには、場面の切り替えで「一緒にジェスチャー」を入れてOK。読み終えられなくても大丈夫、成功体験を優先。
Q. 兄弟で好みが違います。
A. 上の子に“役”を1つお願いして合いの手を入れてもらうと、下の子の集中も保てます。
まとめ:パパの声は“最強のBGM”
うまく読もうと力む必要はありません。大事なのは“同じ時間を共有すること”。忙しい日こそ、5分で良いので一緒にページをめくってみませんか。この記事が、あなたの本棚に新しい一冊を迎えるきっかけになれば嬉しいです。リストは今後もアップデート予定。
「この本も良かった!」という一冊があれば、ぜひコメントで教えてください。
※本記事は筆者(2児の父)の実体験と家庭での反応に基づく個人のおすすめです。医療・発達についての専門的助言が必要な場合は、各専門家へご相談ください。書影・本文の引用は出版社・著者の権利に配慮し最小限に留めています。