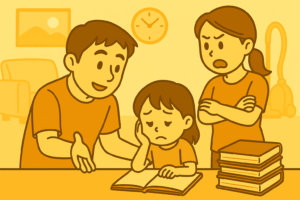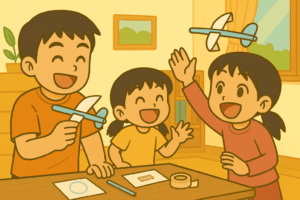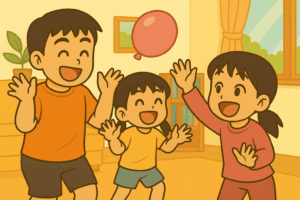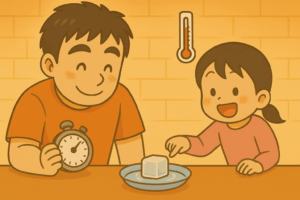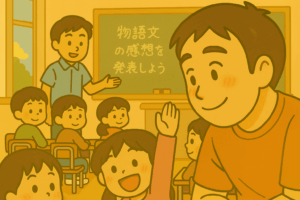こんにちは、二児の娘を育てるパパブロガーのひろゆきです。
今回は、長女が「勉強が楽しくない」とぽつりと漏らした時の話をしたいと思います。
突然訪れた「やる気の消失期」
ある日、リビングで宿題をしていた長女が、鉛筆をポトッと落としながらこう言いました。
「もう分かんない。どうせ私、頭よくないし…。」
普段はコツコツ頑張るタイプの長女。そんな言葉を聞いたのは初めてでした。
算数の文章問題でつまずいていたようで、何度やっても答えが合わない。それがきっかけで一気に自信を失ってしまったのです。
この“自信喪失期”は、どんな子にも一度は訪れるのかもしれません。
ただ、その時の親の言葉ひとつで、子どもの心は大きく変わる——そう感じた出来事でした。
焦らず、まずは「気持ちの整理」から
私も最初は「そんなこと言わずに頑張れ!」と励ましそうになりました。
でも、それでは逆効果だと気づき、ぐっとこらえました。
長女の横に座って、「分からないのは悪いことじゃないよ」と声をかけました。
「パパだって昔、算数で何度も泣いたよ」と少し笑い話にしてみると、長女もクスッと笑いました。
そのあと、「今日はちょっと休もうか」と提案。
一度勉強を離れて、次女も交えてカードゲームをすることにしました。
勉強を嫌いにならないように、“頑張れ”の前に“安心”を与えることを意識しました。
「できた!」を積み重ねる作戦
翌日、少し気持ちが落ち着いたようだったので、一緒に勉強を再開。
でもその時は「テストで満点を取ること」ではなく、「昨日より少しできたらOK」というルールにしました。
難しい問題を避けて、少し簡単な問題を一緒に解きました。
「できた!」と声をあげた瞬間、長女の顔がパッと明るくなりました。
その笑顔を見て、私は心の中でガッツポーズ。
勉強の“楽しさ”は、結局のところ「自分にもできる」と思える瞬間から始まるんですよね。
だからこそ、最初に必要なのは「できる体験」を積み重ねることなんだと感じました。
親がやりがちな「比較の罠」
親として一番気をつけたいのが「他の子と比べること」。
私もつい、「〇〇ちゃんはもう九九全部言えるんだって」と言いそうになってハッとしました。
子どもにとってそれは、「あなたはできていない」という否定のメッセージに聞こえてしまいます。
それよりも、「昨日より速く計算できたね」など、**“過去の自分との比較”**を意識して褒めるようにしました。
すると、少しずつ長女は自信を取り戻していきました。
「前よりできた!」が増えていくと、自然と笑顔も増えていくんですよね。
「勉強=苦しい」から「勉強=ちょっと楽しい」へ
その後、長女には「パパと一緒に勉強ゲーム」を提案しました。
例えば、算数の問題をタイマーで計る「早解きチャレンジ」や、漢字を使った「しりとり大会」。
遊びの中に学びを混ぜると、途端に子どもの表情が変わります。
「勉強=苦しい」から、「勉強=ちょっと楽しい」になった瞬間。
この“ちょっと”がとても大事だと思います。いきなり楽しくはならなくても、苦手意識を和らげるきっかけになります。
次女の存在が“勇気のスイッチ”に
面白いことに、次女が横で「おねえちゃんすごーい!」と素直に褒めた時、
長女が照れながらも嬉しそうに「でしょ?」と返していました。
兄弟(姉妹)って、本当に不思議な関係ですね。
時にはライバル、時には最高の応援団。
この瞬間を見たとき、「家庭の中に“応援”があること」が何よりの学びの原点だと感じました。
親ができる最大のサポートは「寄り添うこと」
子どもが勉強につまずいた時、親として何をしてあげられるか。
それは、“解き方を教えること”よりも、“一緒に考える姿勢”なんだと思います。
長女が「また間違えた」と落ち込んだとき、私はこう言いました。
「間違えたってことは、挑戦したってことだよ。」
この言葉が届いたのか、少しだけ誇らしそうに笑っていました。
おわりに:勉強よりも大切な「自信」を育てたい
子どもが自信を失ったとき、つい“結果”で励ましたくなります。
でも本当に大切なのは、「あなたにはできる力がある」と信じてあげること。
あの日から数週間。
長女は「今日の算数、楽しかった」と言えるようになりました。
テストの点数よりも、その言葉が何よりのご褒美です。
勉強ができる子よりも、「勉強を諦めない子」に育ってほしい。
それが、父親としての一番の願いです。
同じようにお子さんの「やる気スイッチ」が見つからず悩むパパ・ママ、
焦らず、寄り添いながら見守ってあげてください。
きっとその優しさが、子どもの“自信”の芽を育ててくれるはずです。