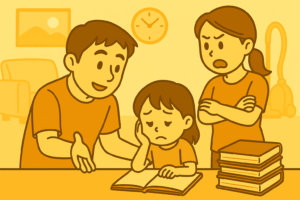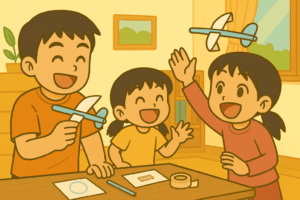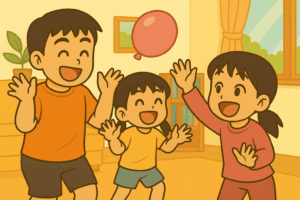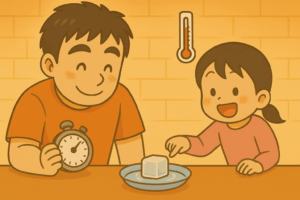こんにちは、二児の娘を育てるパパブロガーのひろゆきです。平日は仕事に追われがちでも、休日は「家族の特別な時間」。娘たちと過ごす我が家の定番「父と子の休日ルーティン」を、準備のコツや小さな工夫も交えてご紹介します。読むだけで明日の休日がちょっと楽しみになるはず。
[toc]
わが家の基本方針|「何をするか」より「誰と楽しむか」
休日の予定は、詰め込みすぎないのが鉄則。子どもは大人よりも刺激に敏感で、予定が多いと疲れやすくなります。そこで我が家では「外遊び1回+おうち時間1回」のようにシンプルな構成に。“予定を達成する”より“笑顔で終える”ことをゴールにしています。
- 予定は最大2本まで(午前と午後で各1本)
- 子ども主体の選択を必ず1つ入れる(遊び・絵本・おやつ等)
- 写真や動画は撮りすぎない(まず目の前の笑顔を優先)
7:00|早起きの声でスタートする朝ごはんづくり
「パパ、おなかすいた〜!」で始まる休日。眠気を連れてキッチンに立ち、ホットケーキや卵焼きを一緒に作ります。ときどきチョコを入れすぎて“真っ黒パンケーキ”が完成することもありますが、それも立派な思い出。手伝いのコツは、役割を“1アクション”で切ることです。
小さな成功体験を積むコツ
- 計量は子どもに任せる(こぼれてもOKの心構え)
- 「混ぜる・のせる・押す」など成功しやすい作業を選ぶ
- 仕上げは必ず「ありがとう」で締める
朝から「できた!」が一つあると、一日中ご機嫌で過ごせます。
9:00|近所の公園へ。“見守り”が主役の時間
徒歩10分の小さな公園でも、子どもにとっては大冒険。すべり台、ブランコ、砂場……最近は長女が補助輪なし自転車に挑戦中。「パパ、見ててね!」と言われたら、スマホはポケットにしまい“拍手担当”に徹します。
ケガ・ぐずり対策の持ち物
- ウェットティッシュ&絆創膏(小さな擦り傷に)
- 凍らせたドリンクor保冷剤(夏場のクールダウン)
- 小袋おやつ(気分転換の切り札)
“転んでも立てた”を一緒に喜ぶことで、挑戦する気持ちが育ちます。
11:30|おうちでランチ。人気は「手巻き寿司ごっこ」
たっぷり遊んだら、次は自宅でお昼ごはんづくり。最近のブームは「手巻き寿司ごっこ」。のりにごはんと具をのせて自分で巻く楽しさに、子どもの食欲もアップします。
手巻き寿司ごっこのポイント
- 具材は3〜4種に絞る(ツナ・きゅうり・卵焼き・カニカマなど)
- 子ども用に“半のり”を用意(巻きやすく、食べやすい)
- 「好きな組み合わせランキング」を一緒に作ると盛り上がる
料理は成果物より過程が宝物。「おいしい!」と笑い合えたら100点満点です。
13:00|お昼寝&クールダウン。何もしない贅沢
午後に向けてエネルギーをためる休憩時間。寝かしつけは“静かな遊び”で導入するとスムーズです。パズルや塗り絵、絵本の読み聞かせで心拍を落ち着かせ、そっと添い寝。となりから聞こえる寝息に「今しかない時間だな」としみじみします。
15:00|午後のお楽しみ。おやつ・絵本・お絵かき・映画
お昼寝から起きたら“ご褒美タイム”。近所のカフェでおやつを楽しんだり、お気に入りの絵本を読んだり、お絵かきでアートセッションをしたり。お家ではAmazonプライムで映画を1本。最近は『トイ・ストーリー』がヘビロテです。
“やりすぎない”ための工夫
- スクリーンタイムは映画1本分を目安に
- おやつは「量より体験」(盛り付けや器選びで楽しむ)
- 記録は数枚の写真だけ。あとは全力で一緒に楽しむ
17:00|お風呂と夜ごはんの準備。遊びに変えるのがコツ
お風呂は娘たちにとってイベント。お湯の温度を少し低めにし、おもちゃを2つだけ持ち込み、長風呂になりすぎないように調整します。シャンプーを嫌がる時は「アワアワ怪獣が来たぞ〜!」と“ごっこ遊び”で変換すると笑顔でクリア。
夜ごはんは「一緒に並べる」から始める
- ランチョンマット・お箸・コップは子ども担当
- メニューは宣言制(「今日は○○が主役!」)
- 「いただきます」の前に感謝を一言ずつ
20:00|絵本タイム&おやすみ前の“ぎゅー”
寝る前は、家族が一番落ち着く時間。布団に入る前に絵本を1〜3冊読み、最後は必ずスキンシップ。子どもが「ぎゅーして」と来たら、今日の楽しかったことを一緒に振り返ります。「楽しかったね」「ありがとう」の言葉で一日を締めくくると、翌朝のご機嫌にもつながります。
トラブルあるあるQ&A
Q. 予定が崩れてイライラ…どう立て直す?
A. 「今日の一番大事をひとつ決める」がコツ。外遊びが無理なら“室内の宝探しゲーム”に置き換えるなど、同じ目的を別の手段でかなえる発想に切り替えます。
Q. 兄妹(姉妹)げんかが勃発したら?
A. まず事実確認よりクールダウン。水分補給→別室で深呼吸→5分後に合流し、選択肢を2つ提示(譲る/交代ルールで続行)。“どちらも正しいポイント”を1つずつ言語化してから解決に進みます。</