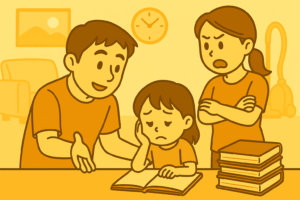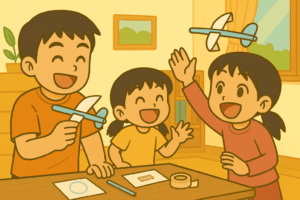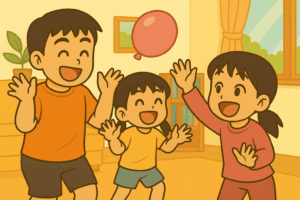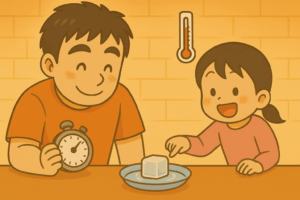[toc]
こんにちは、二児の娘を育てるパパブロガーのひろゆきです。
子どもから「やめたい」と打ち明けられたとき、親にできるのは“止める/続けさせる”の二択ではありません。
本記事では、二児の父である筆者の実体験をもとに、感情に寄り添いながら意思決定をサポートする具体策をまとめました。
1. まずは否定せず「気持ち」を受け止める
最初の一言は「どうして?」ではなく、「何かイヤなことがあった?」「どんな気持ちになった?」と感情に寄り添う質問から。
否定や説得よりも、まず“聴く”が先です。安心して話せる空気をつくると、子どもは本音を出しやすくなります。
質問のコツ(例)
- 「今日はどの場面が一番しんどかった?」
- 「先生やお友だちとのことでモヤっとした?」
- 「通う時間や宿題の量は今の生活に合ってるかな?」
わが家でも、長女は「先生が怖い」「間違えると怒られそう」、次女は「遊ぶ時間が減るのがイヤ」と理由が違いました。
原因の輪郭が分かるほど、解決策は具体化します。
2. 原因を一緒に整理する(分類して考える)
大まかに次の5類型に分けて考えると打ち手が見えます。
- 興味・楽しさの低下…「想像していたのと違った」「達成感が少ない」
- 人間関係…先生との相性/友だち・上級生との関係/チーム内の雰囲気
- 負荷・スケジュール…宿題量・頻度・移動時間が過剰
- 指導スタイル…競技志向が強すぎる/評価が一律で怖い
- 体調・発達ステージ…睡眠不足・成長痛・集中の波など
どれに当てはまるかで、頻度調整/クラス変更/先生への相談/目標の再設計など、取るべきアクションが変わります。
3. 二択にしない:「期限付きで続ける」「条件を変える」
「今すぐやめる/続ける」の二択はプレッシャーになりがち。
まずは“小さな実験”として期限付きで続けるか、条件を変えて試すのが有効です。
具体策
- 期限付き継続:発表会/大会/テストなど一里塚まで続けて、そこで再評価
- 負荷の見直し:宿題量を交渉・練習時間を短縮・通う曜日を変更
- クラス/担当変更:指導スタイルが合う先生やレベル帯へ
- 同伴・見学:不安が強い時は親の同席や友だちと一緒に参加
先生に伝える相談テンプレ
いつもお世話になっております。最近、子どもが「◯◯が不安」と感じているようです。
①状況:◯◯ ②子どもの様子:◯◯ ③お願い:負荷の調整/席替え/宿題量の相談 など
成長の機会は保ちながら、安心感も両立できればと考えています。ご助言いただけますと幸いです。
4. 「目的」を再確認し、目標を小さく再設計する
始めた目的(Will)/今できること(Can)/求められていること(Must)を見直し、小さく達成できる目標に置き換えます(SMART)。
1週間のミニ目標(例:ピアノ)
- 月:右手8小節だけ正確に弾く
- 水:メトロノームでゆっくり1回通す
- 金:録音して「できた点」を3つ見つける
「できた」を見える化すると、自己効力感が戻りやすく、やる気の再点火につながります。
5. やめるか続けるかの目安チェックリスト
以下に3つ以上当てはまれば、やめる選択肢も前向きに検討を。
- 2〜4週間、工夫しても表情・睡眠・食欲の落ち込みが続く
- 人間関係のストレスが強く、改善の糸口が見えない
- 家計・時間の負担が家庭の土台を揺らしている
- 他の活動(遊び・読書・家庭学習)に深刻な支障
- 子どもが自分の言葉で「やめたい理由」と「次にやりたいこと」を説明できている
大切なのは“続ける勇気”と同じくらい“やめる勇気”も尊いと伝えること。選択の主体を子どもに返すことが、長期的な自立につながります。
6. やめた後のフォロー:自己肯定感・代替案・手続き
声かけの例
- 「自分で考えて決められたね。立派な選択だよ」
- 「ここまで続けた経験は消えない。次にも活きるよ」
代替案(ワンステップダウン)
- 個人レッスン→短期ワークショップ/体験会だけ参加
- 週2→隔週/月1に頻度を下げて継続
- ジャンル変更:ピアノ→合唱/作曲アプリで音遊び など
費用・退会の注意
- 退会申請の締日(◯日まで/翌月扱いなど)を契約書で確認
- 月謝の日割り・受講券・教材費の扱いを事前に合意
- レンタル品やロッカーの返却物をメモ化
※各教室の規約が異なるため、必ず契約書・約款を確認してください。
7. まとめ:親子で「今の気持ち」に寄り添い、次の一歩へ
習い事は可能性を広げますが、心の安全基地があってこそ伸びます。
否定せず聴く → 原因を整理 → 小さな実験 → 目的の再設計 → 判断、と段階を踏めば、どの選択でも“学び”に変わります。
親の願いも大切にしながら、最終的な舵取りは子ども自身へ。これがわが家の合言葉です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 「すぐやめたい」と言われたら?
まずは感情を受け止める→安全確保→短期の猶予。危険や強いストレスがある場合は即時中断も選択肢です。落ち着いてから再評価しましょう。
Q2. 先生にどう伝えれば角が立ちませんか?
「子どもの成長を第一に、負荷や参加の形を見直したい」と共同の目的を共有し、具体的な提案(宿題量・クラス変更・期限付き継続)を添えて相談します。
Q3. 何回通わせて判断すべき?
目安は2〜4週間の“試行期間”。その間は記録(気分・睡眠・できたこと)をとり、変化を親子で確認すると納得感が高まります。
Q4. やめ癖がつきませんか?
“やめる理由”と“次に進む計画”を言語化すれば、逃避ではなく意思決定として経験化できます。小さな成功体験を次に橋渡ししましょう。