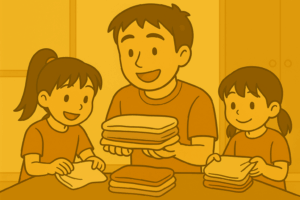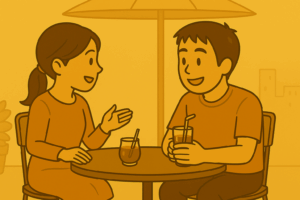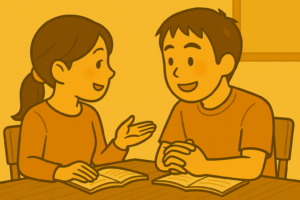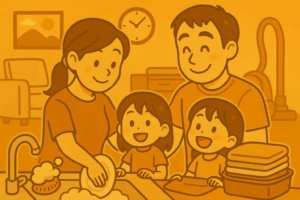こんにちは、二児の娘を育てるパパブロガーのひろゆきです。
父親として、仕事も家庭も一生懸命やっているつもりなのに、なぜか妻の表情が曇っている——。
私自身が感じた「わからなさ」と、そこから抜け出すまでの正直な記録です。
はじめに:わからないままにしない
「どうして怒っているんだろう」「何が不満なんだろう」。
そう思いながらも聞けない。私は長いあいだ、この“保留状態”にいました。けれど結論から言えば、わからないままにしないことが、家族の空気を変える最初の一歩でした。
きっかけは些細な一言だった
ある夜、私は仕事帰りにソファへ直行。テレビをつけた瞬間、妻が小さくつぶやきました。
「あなたはいいよね。家に帰ってきたら“お疲れ様”で終われるんだから」
私にとって家は「休む場所」でしたが、妻にとっては「終わりのない仕事場」になっていた——その視点を、私は持てていませんでした。
「わかっているつもり」が一番の落とし穴
仕事を頑張る自分に満足して、「家事の大変さ」だけを問題だと決め付けていた私。
そんな時、次女の一言が胸に刺さります。
「ママ、最近よく泣いてるよ」
必要だったのは手伝いより先に気持ちへの共感でした。私は「何をしてほしいか」ばかりを聞き、「どんな気持ちか」を受けとめていなかったのです。
話を“聞く”ではなく“受けとめる”
勇気を出して聞いた夜
「最近、ちょっと元気ないよね。俺、何かできることある?」
最初は「別に」と言っていた妻も、少しずつ本音を話し始めました。
「子どもたちの世話も、学校の連絡も、家のことも全部私。あなたが悪いわけじゃないけど、
“私も頑張ってる”ってことを見てほしい。」
この言葉で気づきました。私はいつの間にか「ありがとう」を言わなくなっていたのだと。
解決策よりも「最後まで聞く」
- 途中で結論を出さない(アドバイスは求められてから)
- 共感を言葉にする(「それはしんどいね」「大変だったね」)
- 事実と感情を分けて聞く(何が起きた?どう感じた?)
夫婦はチーム:言葉にして伝える
日常で増やした3つの習慣
- 小さな「ありがとう」を可視化(洗い物・連絡帳・お弁当など都度伝える)
- 家事の“前工程”を持つ(配膳の下準備、洗濯の仕分け、保育園/学校の提出物整理)
- 週1の5分MTG(予定・負担・助けてほしいことを共有)
言葉は小さいけれど、心を繋ぎ直す力があります。子どもたちも自然と「ママ、ありがとう」と言うようになり、家庭の空気が柔らかくなりました。
サインを見逃さない:察するより、感じ取る
“察する”よりも“感じ取る”。私は小さなサインをメモするようにしました。
- 口数が減る、返事が短い(「うん」「別に」)
- ため息や独り言が増える、夜更かしが続く
- 子どもへの注意が増える(余裕のなさのサイン)
サインに気づいたら、「どうしたの?」と一言だけ聞く。その後は、焦らず最後まで聞く。
これだけで関係は少しずつ良くなりました。
具体的にやって良かったこと(ミニチェックリスト)
- 帰宅後の最初の言葉を固定:「今日もありがとう。何から手伝う?」
- 家事の見える化:タスク表を冷蔵庫に貼り、当日の担当を交代制に
- 「1人時間」確保:土日のどちらかは妻のフリータイムを必ず設定
- 感謝のログ:寝る前に感謝を1つずつ言い合う
- クールダウン・ルール:言い合いになったら15分離れて水を飲む
よくあるすれ違いと私たちの対処
①「手伝うよ」問題
「手伝う」は主担当が妻の前提。
→ 「分担しよう」「今日は自分が主でやるね」に言い換える。
②「言ってくれればやるのに」問題
指示待ちは二重負担。
→ 自分で見つけ、自分で締め切りを切る(例:20時までに洗濯と弁当下ごしらえ)。
③「それくらいならできるでしょ?」問題
負担感は人それぞれ。
→ 作業時間で比べず、気力消耗を見積もる(「今日は気力どれくらい?」と確認)。
まとめ:完璧じゃなくていい、続ければいい
夫婦はチーム。
「わかってくれているはず」を捨てて、「聞いてみよう」に置き換える。
それだけで、家族はゆっくりと良い方向に転がりはじめます。
今日の夜、たった一言でいいので聞いてみてください。
「最近どう?今週はどこを自分が持つ?」
おわりに:読者のあなたへ
父親として、夫として、私もまだ道半ばです。
それでも、“受けとめる”を続けたら、家の空気が変わりました。
この記事が、あなたのご家庭の会話を一つ増やすきっかけになれば嬉しいです。